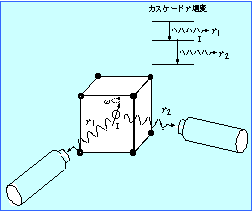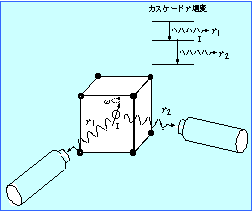

物性物理学部門
大学院基礎工学研究科物理系専攻の教職員や院生、基礎工学部電子物理科学科学生によって
利用され、以下のような研究がされています。
物性物理学部門では放射性同位元素(RI)から出てくる放射線のうち、電磁波(光子)であるγ(ガ
ンマ)線、および陽電子(電子の反粒子)線であるβ+(ベータ・プラス)線を利用し、文字通り物質の
性質を調べる物性研究に応用しています。物質には電気の流れやすいもの流れにくいもの、磁石に
付くもの付かないものなど、さまざまな性質がありますが、この性質を左右するのは物質を構成する
原子の並び方、そして原子の中の電子の運動(実は電子状態と言います)であることが知られていま
す。物性物理学という言葉はあまり耳慣れない言葉かもしれませんが、物質の性質とそれを引き出
す原子の並び方や電子の運動との不思議な?
関連を深く追求しようとする学問で、ここRIセンター
では放射線を調べる道具として使う訳です。
さて、具体的に物性部門で行っている実験の方法には
γ線を利用した(1)γ線摂動角相関法(PAC)と (2)メスバウアー分光法、
β+線を利用した(3)陽電子消滅分光法があります。
(1)のγ線摂動角相関法で用いるγ線は透過力が強いので、いろいろな物質にRIを埋め込むこと
により、調べることが出来ます。 このγ線摂動角相関法では短い時間(10−9秒程度、ns、ナノ・セ
カンドという単位を用います)の間に2つのγ線を続けて放射する
(カスケード壊変と言います)ような
RIを用います。1つ目のγ線の放射方向を基準にすると2つ目のγ線は放出しやすい方向としにくい
方向があり、それを角相関があると言います。例えば電子状態の変化から原子が磁石的な性質(磁
性)を持つようになると、この角相関が時間と伴に変化することが知られています。角相関の時間変
化をいくつかの検出器で測定することにより、逆に原子の持つ磁性に関する情報を調べることが出来
ます。